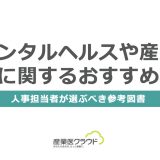はじめに:なぜ4つのケアが重要なのか?
職場でのメンタルヘルス対策は、従業員の健康維持だけでなく、生産性や離職率にも直結する重要な課題です。
「4つのケア」は、従業員、管理職、産業保健スタッフ、外部リソースが連携し、包括的に問題を解決するための指針です。
メンタルヘルス対策は、主に、「休職対策」と「予防」に大別されます。
「4つのケア」は「予防」に該当します。留意してほしい事項は、あくまで「予防」なので、即効性はありません。
即効性がある施策は「休職対策」です。
休職に関しては、こちらをご参考ください。
産業医や産業保健師による復職支援の重要性
コミュニケーションや事務能力に疑問…
質の高い産業医に依頼したいとお考えではないでしょうか?
産業医紹介サービスを検討している企業様必見!
産業医クラウドなら独自の研修を受け、スキルチェックも通過した、厳選された産業医をご紹介します。
→「産業医クラウド」のサービス資料を見る
1. メンタルヘルスの4つのケアとその目的
セルフケア
セルフケアの目的は、従業員が自身のストレス状態を認識し、適切に対処する力を身につけることです。
具体的な取り組みとして、ストレスチェックの結果を活用した研修や、リラクゼーション法を学ぶワークショップの開催が挙げられます。
また、マインドフルネスや定期的な運動を取り入れるよう推奨する企業もあります。
従業員が自身の健康状態に責任を持ち、自律的に行動できるよう支援することが、職場全体のストレス軽減につながります。
弱点として、個々人の行動変容に依存するため、エビデンスレベルがあるほど、研修等に効果が見えづらいということがあります。
また、「セルフケア」という言葉自体が、聞き慣れない言葉だということです。医療従事者では普通の言葉でも、一般的な労働者には馴染みがなく、遠い世界のように感じてしまいます。
「セルフケア」は「コンディショニング」と言い換えたほうが、馴染みがあるかもしれません。
ラインケア
ラインケアは、管理職が従業員の日常的な健康状態を把握し、不調の兆候に早期対応することを目的とします。
多くの「ラインケア」の解説では以下のような内容がなされるでしょう。
1on1ミーティングを活用して従業員とのコミュニケーションを強化し、不安や悩みを共有できる環境を整備します。また、管理職向け研修を実施し、不調サインを見抜くスキルや適切な対応方法を習得させることが重要です。管理職が積極的に関与することで、メンタル不調の早期発見と対応が可能になります。
内容は一定の価値はあるものの、現実的には、これも上司の能力に依存するため、効用という側面で見ると、トップのコミットメントがない限り、実現は難しいです。
例えば、全ての上司が、コミュニケーションスキルが高く、1on1で部下の不安や悩み等を解決できるほど、現代社会は単純ではありません。
管理職向け研修等で、「部下の不調サインやスキル」等を見抜けるようになるほど、単純でもありません。
産業保健スタッフ等によるケア
産業保健スタッフ等によるケアは、産業医や産業保健師が専門的な知識を活用して従業員を支援することを目的とします。
多くの解説では、「産業保健スタッフ等によるケア」を下記のように解説しています。
健康診断やストレスチェックの結果を基に、高ストレス者への面談や職場環境の改善提案を行います。加えて、産業医による職場巡視や、従業員個別の健康相談も重要な取り組みです。
このケアにより、従業員の健康リスクを効果的に管理し、職場全体のメンタルヘルス向上を図ることができます。
しかし、現実的には、産業医や産業保健師が、高ストレス者に面談したからといって、面談社のメンタルが改善することは、まず、ありません。
また、よほどの産業保健に対する経験業種ごとにおける職場環境の熟知、直近ではDX化の流れやAIの流れを知らずに「職場環境の改善提案」は、産業医や産業保健師が主体的に動くことは難しいです。
では、どうすると良いのかというと、あくまで、産業医や産業保健師が、企業や自治体の組織におけるセフティーネットとして機能させることを目的とすることです。
メンタル不調かもしれないと感じている従業員が、産業医や産業保健師に対し、信頼を持って、打ち明けられ、相談できることが重要です。
これが機能し始めると、産業保健スタッフによる早期介入がしやすくなり、結果的にメンタル不調に陥りそうな従業員の休職を回避できる確率が増します。
事業場外資源によるケア
事業場外資源によるケアは、企業内で解決が困難なケースに対し、外部の専門機関を活用することを目的とします。
「事業場外資源によるケア」も、一般的には下記のように説明されるケースが多いでしょう。
EAP(従業員支援プログラム)や外部のカウンセリングサービスを導入することが挙げられます。
また、メンタル不調が深刻な従業員には専門医療機関を紹介し、早期の治療を支援します。これにより、企業内のリソースを効率的に活用しながら、深刻な問題に対処する仕組みを構築できます。
しかし、現実的には、この施策がメンタルヘルスの不調者を減らすや、休職率を下げるという結果は得られません。
EAP等のカウンセリング環境のセフティーネットは重要ですが、個人のプライバシーに関する相談も少なくなく、企業におけるメンタルヘルス課題の解決に資する情報を、企業が得にくいということが弱点です。
コミュニケーションや事務能力に疑問…
質の高い産業医に依頼したいとお考えではないでしょうか?
産業医紹介サービスを検討している企業様必見!
産業医クラウドなら独自の研修を受け、スキルチェックも通過した、厳選された産業医をご紹介します。
→「産業医クラウド」のサービス資料を見る
2. 各ケアの具体的な内容と取り組み
2-1. セルフケア:従業員自身によるストレスマネジメント
セルフケアでは、従業員が自身のストレスに気づき、適切に対処するスキルを習得することが重要です。
具体的な取り組みとして、サンプルの動画が欲しい方は、こちらまでお問い合わせください。代表の刀禰による研修動画を送ります。
代表の刀禰は多くの企業、自治体等でメンタルヘルス研修やセミナーを行っています。
(例)第一生命保険、株式会社アウトソーシング、栃木刑務所、大阪府公務員、
2-2. ラインケア:管理職によるメンタルヘルス支援
ラインケアは、管理職が部下のメンタルヘルスを支援する役割を担います。
一般的な「ラインケア研修」では下記の内容になります。
1on1ミーティングを通じて部下のストレスや不安を把握し、不調の兆候に早期に気づく仕組みを構築します。
管理職向けの研修を実施し、不調の兆候を見抜くスキルや適切な対応策を学ばせます。
さらに、産業医や人事部と連携することで、深刻なケースに迅速に対応できます。管理職の積極的な関与が職場全体の健康維持に直結します。
しかし、これでは、複雑すぎて、管理職も3日で忘れてしまいます。もっとシンプルに、わかりやすい言葉で、管理職の納得感があり、管理職の行動変容につながる内容にしなければなりません。
具体的な取り組みとして、サンプルの動画が欲しい方は、こちらまでお問い合わせください。
代表の刀禰による研修動画を送ります。
代表の刀禰は多くの企業、自治体等でメンタルヘルス研修やセミナーを行っています。
(例)第一生命保険、株式会社アウトソーシング、栃木刑務所、大阪府公務員、
2-3. 産業保健スタッフ等によるケア:専門的な支援
産業保健スタッフ等によるケアは、産業医や産業保健師が専門知識を活用して従業員のメンタルヘルスを支援する取り組みで、健康診断やストレスチェックの結果を基に、高ストレス者への面談や、必要に応じた業務負荷の調整提案を行います。
また、産業医は職場巡視を通じて労働環境を評価し、改善策を提案します。
このケアは、従業員個別の問題に対処しつつ、職場全体のリスク軽減に寄与します。
上記が一般的な、「産業保健スタッフ等によるケア」ですが、現実は、そんなに甘くありません。
先程も述べたように、産業医や産業保健師が、従業員から信頼され、指名で相談される関係づくりをゴールとし、産業保健スタッフが早期介入できる環境づくりの方が、再現性高く実現できます。
2-4. 事業場外資源によるケア:外部リソースの活用
事業場外資源によるケアでは、外部の専門機関やサービスを活用し、企業内で対応が難しいケースをサポートします。
所謂、EAP(従業員支援プログラム)を導入し、従業員が匿名で専門家に相談できる環境を整備します。また、深刻なメンタル不調者には、専門医療機関への紹介を迅速に行います。
これにより、企業内のリソースを効率的に使いながら、従業員の健康維持と早期回復を支援できます。
コミュニケーションや事務能力に疑問…
質の高い産業医に依頼したいとお考えではないでしょうか?
産業医紹介サービスを検討している企業様必見!
産業医クラウドなら独自の研修を受け、スキルチェックも通過した、厳選された産業医をご紹介します。
→「産業医クラウド」のサービス資料を見る
3. 4つのケアを導入する際の注意点
- 社内での共通理解を形成
4つのケアの目的や役割を全従業員に周知。 留意点は、セルフケア、ラインケア、産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアという言葉を使わないこと。良い言葉に言い換えてください。 - 個人情報とプライバシーに関する情報の整理
よく、こちらが混同されるケースが多いので、メンタルヘルス研修だけではなく、個人情報保護、プライバシー情報の定義、情報管理に関する研修等を年間計画に必ず入れることを推奨します。 - 継続的な評価と改善
取り組みの効果を測定し、定期的に改善を行う。
4. 導入ステップとチェックリスト
| ステップ | アクション例 |
|---|---|
| 現状分析 | アンケートやストレスチェックで職場の課題を特定。 |
| 計画立案 | 4つのケアを組み合わせた実施計画を策定。 |
| 全社的な展開 | 各部門での研修やプログラムを実施。 |
| 評価と改善 | 定量的データ(休職率、満足度)を基に取り組みを改善。 |
まとめ
メンタルヘルスの4つのケアは、あくまで「メンタルヘルス予防」の指針です。
人に当てはめれば直感的に理解できますが、「予防」は日々の習慣化が最も重要であり、効果が出るまで時間がかかります。それを理解した上で実行することを念頭においてください。
一方で、人のフィジカルもメンタルも、「予防習慣」がなければ、一定の期間で体調不良を引き起こしますので、現代社会において、このプログラムを実施しないということは、「予防しない」と同義であると理解できるでしょう。
コミュニケーションや事務能力に疑問…
質の高い産業医に依頼したいとお考えではないでしょうか?
産業医紹介サービスを検討している企業様必見!
産業医クラウドなら独自の研修を受け、スキルチェックも通過した、厳選された産業医をご紹介します。
→「産業医クラウド」のサービス資料を見る